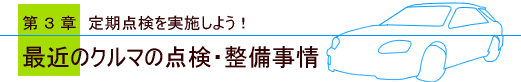| 令和5年1月から自動車検査証(車検証)が変わりました! |
|
| 令和5年1月より紙の車検証から、順次、電子車検証に切り替わります。(軽自動車についても令和6年1月から電子車検証への切り替えが始まりました。)電子車検証では、用紙サイズがA4からA6にコンパクトになり、また、ICタグが内蔵され、その中に従来、自動車検査証に記載されていた全ての情報が記録されています。ユーザー本人が電子車検証の情報を確認するためには、スマートフォンなどで、下記QRコード※から「車検証閲覧アプリ」をダウンロードして、ICタグを読み取ることで可能となります。 |
| ※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 |
| 表 面 |
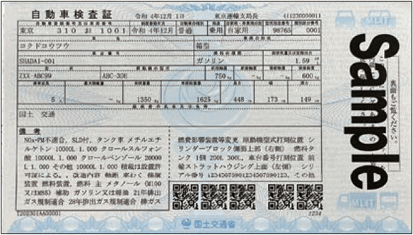 |
|
| 裏 面 |
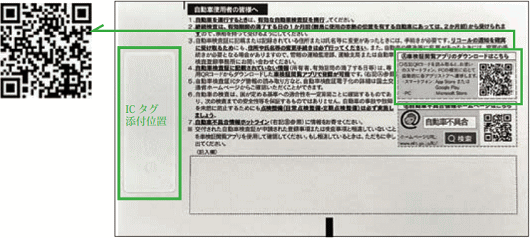 |
|
|
| 詳しくは、「電子車検証特設サイト」よりご確認ください。 |
| https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/ |
|
| 車検証に点検整備の実施状況が記載(記録)されています |
|
| 自動車の使用者には点検整備の実施が義務付けられていますが、自動車ユーザーが車検時の定期点検整備の実施状況等を確認できるよう、登録自動車・軽自動車及び二輪の小型自動車の車検証の備考欄には点検整備実施状況等が記載されています。定期点検整備を実施している場合は「点検整備記録簿記載あり」、点検整備の実施が確認できなかった場合には「点検整備記録簿記載なし」と記載してあります。もし車検証に「点検整備記録簿記載なし」と書かれていたら、整備工場で定期点検整備を実施しましょう。なお、電子車検証の場合は、ICタグに記録されていますので、「車検証閲覧アプリ」で備考欄情報をご確認ください。 |
|
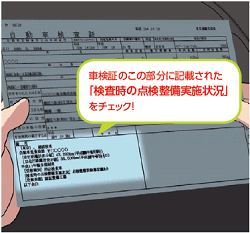 |
|
|
| ハイブリッド車およびEV車(電気自動車)の注意点 |
|
| 最近増えているハイブリッド車やEV車(電気自動車)は、クルマを動かすほどの動力を電気的に発生させるため、高電圧部位が存在します。扱いを間違うと感電などの危険があり、最悪の場合死亡事故に至ってしまうケースも考えられます。クルマのトラブルなどが発生した場合は、自分で触らず速やかに整備工場へ連絡しましょう。 |
 |
|
| エコカー等の部品別留意点 |
|
|
|
| アイドリングストップ車は、エンジン再始動時に効率的に安定した電力供給(放電)を行う必要があります。必然的にバッテリの使用頻度が高くなるため、アイドリングストップ&スタート時の頻繁な充放電の繰り返しに耐えられる専用バッテリが必要になります。 |
|
|
|
| エコカー等には転がり抵抗を減らすことにより通常のタイヤよりも省燃費性能を上げる専用省燃費タイヤが装着されていることがあります。これを通常のタイヤに変えた場合、本来の燃費性能が発揮されない場合や適性空気圧に設定できないことがありますので、交換の際は整備工場に相談しましょう。 |
|
|
|
| 低燃費エンジン搭載車、ハイブリッド車には、粘度を低く(サラサラに)することによりエンジンの負荷を減らし燃費を向上させる省燃費オイルが使われています。しかし年式の古い車の場合、省燃費オイルに対応していない可能性があるので、交換の際は整備工場にて確認しましょう。 |
|
| 点検整備の現場で活躍するスキャンツール(外部診断器) |
|
目覚ましい技術革新により、クルマの利便性は日々向上しています。低燃費性能の追求や安全性向上等のため、エンジンはもちろん、ブレーキやステアリング操作等を統合的にコントロールしているクルマも数多く存在します。そうしたクルマは電子制御装置を多用しているため、スキャンツールを使わなければ状態を正確に把握することが困難です。スキャンツールとは、車両に接続しコンピュータと通信を行い、解析及び整備するための情報を表示できる機器で、言わばクルマの状態を「見えるようにする道具」です。クルマが便利になった分、その点検・整備には専門の機器と高度な知識や技術が必要となるのです。
平成25年からスキャンツールを有効に活用し、自動車の電子制御装置の機能診断を行うことで的確なアドバイスや修理ができる整備工場を『コンピュータ・システム診断認定店』として認定しております。認定店は、「コンピュータ・システム診断認定店」の名称が入った卓上盾やのぼり旗、看板を掲げておりますので、クルマが不調になってしまった場合以外でもクルマの健康状態をチェックしたい場合には、お近くの『コンピュータ・システム診断認定店』へお気軽にお立ち寄りください。 |
|
|
|
| コンピュータ・システム診断認定店 |
|
 |
|
|
 |
最近のクルマは構造が複雑になり、必要な点検・整備が増えています。
詳しくはお近くの整備工場でお尋ねください。 |
|
|
|
| OBD点検・OBD検査とは? ~スキャンツールを用いて電子的な不具合を発見します!~ |
|
| 衝突被害軽減ブレーキやレーンキープアシストなどを装備する先進安全自動車は、交通事故の防止に大きな効果が期待されますが、故障時には誤作動による事故などにつながる恐れがあります。機械部分の点検とともに目に見えない電子部分も点検や検査をすることで故障を未然に防ぎ、その性能維持を図ります。 |
|
| OBD点検 |
法定1年定期点検で義務付けられている点検です。 |
|
OBD点検は、「整備用スキャンツール」をOBDコネクタに接続し、車両の「OBD※1」が記録している
各装置の故障(DTC※2)の有無を読み出すことで、各装置が正常に作動しているかを点検します。
過去の故障も記録している装置もあり、気付きにくい不具合も把握できます。 |
|
|
|
OBD検査※3は、従来の検査では発見できなかった電子制御装置の故障の有無に反応する電子的な検査
で、車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録する「OBD」から「検査用スキャン
ツール」を用いて、車両に記録された「特定DTC」を読み取り、完成検査時に合否判定を行います。 |
|
※1:OBDとは、車両に搭載されたコンピュータが各種装置の状態を監視するとともに、故障の有無
を記録する装置です。 |
| ※2:DTCとは、車両故障時にコンピュータが記録する故障コードです。 |
※3:OBD検査対象車は、国産車は令和3年10月1日以降の新型車、輸入車は令和4年10月1日以降の
新型車になります。(OBD検査対象車両は車検証の備考欄に記載があります。) |
|
OBD点検やOBD検査の他にも、指定工場では車検受入れ時に、認証工場で
は車検場に持ち込む前などに「特定DTC」の有無を確認し、事前に異常が
ないことを確認する「OBD確認」という作業を行うこともあります。
完成検査前にOBD確認を行うことで、追加整備の発生や再検査などの未然
防止につながり、その結果、車両預かり期間の長期化防止が図られます! |
 |
|
|
| 長期間使用したクルマの点検整備って? |
|
| 近年、クルマを大切に長期間使用するユーザーが増えています。長期間使用したクルマはユーザーが気付かないうちに各種部品が摩耗・劣化するもの。そのまま使用し続けると、突然重度の故障に陥るだけでなく、交通事故などのリスクを背負うことにもなります。さまざまなリスクを回避するため、自動車整備業界では、長期使用車両向け点検整備推奨項目を設けています。長期使用車両に多く見られる故障部位を中心に点検整備項目を設定しているので、クルマのトラブル防止効果が期待できます。整備工場とも息が長いおつきあいができるといいですね。 |
|
| ● 長期使用車両(自家用乗用車)点検整備推奨項目 |
| 推 奨 点 検 項 目 |
| 各種ペダルパッドの摩耗 |
| サスペンションの状態(機能の低下、ショックアブソーバおよびスプリングのへたり) |
| クラッチの作用 |
| プロペラシャフトのジョイント部およびベアリングのがた |
| ドライブシャフトのジョイント部およびベアリングのがた |
| プラグコードの状態 |
| ラジエータキャップの状態 |
| エンジンマウントラバーおよびブラケットの状態 |
| インジケータランプの点灯状態 |
| シートベルトの損傷、作用 |
|
|
| 推 奨 交 換 部 品 |
| ブレーキホースの交換 |
| ブレーキマスターシリンダのゴム部品(インナーキット)の交換 |
| ディスクキャリパ・ホイールシリンダのゴム部品(インナーキット)の交換 |
| スパークプラグ(白金・イリジウム)の交換 |
| フューエルフィルタの交換 |
| フューエルホースの交換(エンジンルーム) |
| クーラント(LLC、冷却水)の交換 |
| タイミングベルトの交換 |
|
| (参 考)定期点検と併せて実施すると、より効果的です。 |
|
| ● 長期使用車両(自家用乗用車)故障事例 |
|
|
| ※ 画像をクリックすると印刷用PDFデータが別ウインドウで開きます。 |
|
環境問題への関心が高まる現在、適切な点検・整備を実施することで約2%の燃費改善効果を得られることが実証されています※。
環境保全にもつながる定期点検、その重要性を認識するとともに適切な点検・整備の実施を心がけましょう。 |
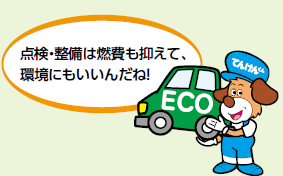 |
|
|
|
|
|