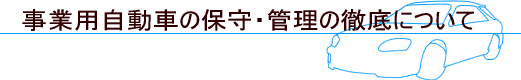| 今般、北陸信越運輸局では、平成25年11月に発生した、管内のバス事業者が運行する高速乗合バスの高速道路における事故について、車枠主要構造部位の凍結防止剤等による塩害の影響が大きい腐食が主な原因であると推測し、管内の高速乗合バスを運行する事業者等にバスの腐食による影響を調査したところ、冬期間に使用される凍結防止剤あるいは塩風等による塩害の影響が大きいことが確認されるとともに、近年、当該事故以外にも車両故障事故が多数報告されていることから、管内の支局長に対し、標記に係る注意喚起を管内関係団体に実施するよう要請しました。 |
| また、本件について、国土交通省においては、各地方運輸局に対し、同様の注意喚起を要請するとともに、その旨の通知が日整連に対し別紙のとおりありました。 |
| つきましては、凍結防止剤、塩風等による塩害を受けている車両に対しては、腐食の状況等を確認し、自動車使用者に適切なアドバイスをして頂きますようお願い致します。 |
| なお、今回の国土交通省における対応は、緊急対策として行うもので、抜本的な再発防止策については、「使用過程車の保守管理に関する調査分析検討会」に依頼する等して発生原因を究明し、その内容に応じて検討、取りまとめを行った上で講じる予定となっております。 |
|
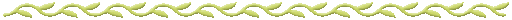 |
|
| 別 紙 |
|
国自整 第365号の2
平成26年03月07日 |
|
| 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 |
|
| 国土交通省自動車局整備課長 |
|
| 事業省自動車の保守管理の徹底について |
|
| 標記について、別添のとおり地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので、参考までにお知らせします。 |
|
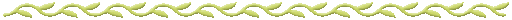 |
|
| 別 添 1 |
|
国 自 整 365 号
平成26年03月07日 |
|
地方運輸局自動車技術安全部長 殿
沖縄総合事務局運輸部長 殿 |
|
| 自動車局整備課長 |
|
| 事業用自動車の保守管理の徹底について |
|
| 今般、北陸信越運輸局より、平成25年11月1日に山梨県内の中央自動車道(下り線)で発生した管内のバス事業者が運行する高速乗合バスの人身事故(乗客5名が負傷。フロントメンバーが脱落し、ハンドル操作が不能となったことにより発生。車枠主要構造部位の凍結防止剤等による塩害の影響が大きい腐食が主な原因であると推測)について、自動車事故報告書等を踏まえ、当局管内の運輸支局長に対し、別添のとおり事業用自動車の保守管理徹底に係る注意喚起を管内関係団体に対し実施するよう通知した旨の報告があったので、参考までに送付する。 |
| ついては、貴部においても同種事案の事故を未然に防ぐため、別添を参考に、管内の支局長を通じる等により関係団体に対する注意喚起、指導に努められたい。 |
| なお、今回の対応は緊急対策として行うものであり、抜本的な再発防止対策については、「使用過程車の保守管理に関する調査分析検討会」に依頼する等により、発生原因は究明し、その内容に応じて検討、取りまとめを行った上で講じる予定としていることを申し添える。 |
|
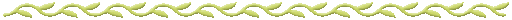 |
|
| 別 添 2 |
|
北信技整第 230号
北信技保第 123号
平成26年02月25日 |
|
| 石川運輸支局長 殿 |
|
| 北陸信越運輸局 自動車技術安全部長 |
|
| 事業用自動車の保守・管理の徹底について |
|
| 自動車運送事業に使用される自動車の保守管理については、これまでも機会を捉え、指導等してきたところであるが、昨年11月に高速道路を走行していた高速乗合バスが、ハンドル操作が不能となり、中央分離帯を乗り越え対向車線に飛び出し、路肩ガードレールに衝突した後、追い越し車線で停車し、乗客5人が負傷する事故が発生した。 |
| 当該事故の原因については自動車事故報告書等から車枠主要構造部位の腐食が主な原因であると推測できることから、今般、管内の高速乗合バスを運行する事業者等の協力を得て、バスの腐食による影響を調査(以下「腐食調査」という)したところ、別添のとおりの結果であり、冬期間に使用される凍結防止剤あるいは塩風等による塩害の影響が大きいことが確認されたところであるとともに、近年、当該事故以外にも、車両故障事故が多数報告されていることから、これらの状況に鑑み、事業用自動車の保守管理について、いっそう徹底を図るよう、下記について関係団体等に対し強力に指導願いたい。 |
| なお、当該事故が高速乗合バスで発生していることから、バス事業者に対しては全車両について早急に腐食状況等の点検を実施させ、点検結果とその対応策について別紙により4月25日までに報告すること。 |
|
| 記 |
|
1.当該事故及び腐食調査の結果等から、凍結防止剤の影響が大きいと考えられることから、凍結
1.防止剤付着に対する対策(防錆剤の塗装、運行後のこまめな下部洗車、腐食の程度を確認する
1.ための点検ハンマーによる打音点検 等)を実施すること。 |
|
2.自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則第45条(点検整備等)第1項又は貨物自動
2.車運送事業輸送安全規則第13条(点検整備)第1項に基づき、運行する道路の状況、走行距離
2.等使用の条件を考慮した点検基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。 |
|
3.上記2.については、整備担当部署、又は点検を依頼する整備工場との連携を密に行い、運行
3.する道路状況等を考慮した点検基準の作成を依頼することについては差し支えない。 |
|
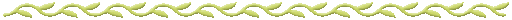 |
|
| 凍結防止剤散布の影響と思われる車両(バス)不具合の発生状況と対応調査について |
|
| 北陸信越運輸局自動車技術安全部 整備・保安課 |
|
| 25年11月に管内事業者の高速バスが中央道を走行中に、フロントメンバが腐食により脱落し、ハンドル操作が不能となり、中央分離帯を乗り越え、反対車線で停止し、軽傷者が発生する事故を惹起した。幸い走行車両がなかったことから大事故にはならなかったものの、重大事故になる可能性のある事故であったことから、腐食の原因と考えられる凍結防止剤散布による車両への影響と対応について、特に高速道路を運行する管内バス事業者26社にアンケートをお願いし、その結果についてまとめたものです。 |
|
|
質問事項 |
各社からの回答 |
| Q1 |
下廻りに腐食等の発生はあり
ますか? |
26社中18社が車両に腐食があると回答 腐食あり69%
|
| Q2 |
腐食がある場合、保有車両の
何割程度に腐食がありますか? |
~40%:9社 |
腐食が確認された18社中、半数の9社が
保有車両の5割以上の車両に腐食が発生
していると回答 |
| 50~100%:9社 |
| Q2-2 |
腐食防止の対策はしています
か?(腐食がない場合) |
腐食がないと回答のあった8社中7社が対策実施
87%が実施 |
腐食防止の対策はしています
か?(腐食がある場合) |
腐食があると回答のあった18社中16社が対策実施
89%が実施 |
| 腐食防止対策の内容は? |
下廻りへの防錆剤やシャシブラックの塗装、高圧洗車機
の導入、使用6年でのボディ補修、こまめな下廻り洗車、
下廻り厚めに塗装 等 |
| Q3 |
過去に凍結防止剤散布の影響
と思われる不具合の発生はあ
りましたか? |
あり62%(26社中16社があると回答) |
| Q4 |
保有車両の何割程度に不具合
が発生しましたか? |
30%以下:9社 |
あると回答のあった事業者の内、約4割
の事業者は、保有車両の4割以上の車両
に不具合が発生していると回答 |
| 40~60%:6社 |
| 70%以上:1社 |
| Q5 |
不具合の発生した部位はどこ
ですか? |
デフの腐食、穴あき、オイル漏れ/ホーシング/トランク
下部の腐食/チェンジロッド/アクスル関係/フレーム、
サブフレーム、メンバ腐食/エアサスブラケット/下部骨
格全体/パワステパイプ腐食によるオイル漏れ/オイルパ
ン穴あき/Fジャッキアップポイント部/Fフェンダ内部等
※ 腐食の発生箇所は車両後部に多く発生している。これ
は付着した凍結防止剤がエンジンの熱により腐食が進
んだものと考えられる。 |
| Q6 |
定期的に腐食に対する点検や
整備を行っていますか? |
定期的に行っている:26社中22社
85%が定期的に行っている。
※ 定期的に行っていない4社のうち、腐食がないと回答
があった事業者は2社で、各社腐食がなくても定期的
に点検を行っていることが伺える。 |
| Q7 |
定期的に点検を行っている場
合、どの程度の間隔でどこの
点検を行っていますか? |
2週間ごと:1社、1ヶ月点検時:6社、3ヶ月点検時:10社
12ヶ月点検時:3社、その他:6年後ごとに修繕1社、10年
目に修繕:1社
点検箇所は下廻り全般について点検が18社、エンジン/
クロスメンバ/サスペンション/ブレーキ関係/ステアリン
グ等が4社
※ 点検方法については、ほとんどが目視による点検。
※ 点検部位によっては点検ハンマーによる打音点検も
必要と思われる。 |
| Q8 |
Q7の点検については、社内規
程等により基準が定められて
いますか? |
社内規程等で定められている:2社
定められていない:24社
※ ほとんどの事業者が社内規定では点検基準は定められ
ていない。各社独自に定期的に点検する部位を定めて
いるが、旅客自動車運送事業運輸規則第45条第1項に
よれば、「…並びに運行する道路の状況、…を考慮し
て、定期に行う点検の基準を作成し、…」と定められ
ていることから、点検基準を定め、これにより点検、
整備をしなければならない。 |
| Q9 |
点検の結果、修理が必要と認
められた場合、修理はどこに
依頼しますか? |
自社整備工場及びグループ内整備工場:9社
整備専業工場、ディーラー、車体整備工場:17社 |
|
|
| ○ 回答に対する考察 |
|
| 1.調査を実施した高速道路を運行するバス事業者26社の内、約7割にあたる18社の車両に腐食が認められ、そのうちの9社は保有車両の5割以上の車両に腐食が認められた。腐食の原因は、散布された凍結防止剤が付着したことによるものが主な原因と考えられる。 |
|
| 2.回答のあった事業者26社の内、腐食防止対策をしている事業者は23社で、対策をしていない事業者は3社しかなかった。(腐食があっても未対策の事業者2社、腐食がなく未対策事業者1社)車両(バス)の使用期間が長期化している中で、腐食防止対策を実施することは必要不可欠となっている。また、腐食がなくても腐食防止対策を実施している事業者がほとんどであり、腐食防止が重要となっている。 |
|
| 3.過去に凍結防止剤散布の影響と思われる車両の不具合は26社中16社で発生している。そのうち7社で保有車両の4割以上の車両に不具合が発生している。不具合の発生部位について、事業者から話を聞くと、車体の後部、エンジン付近に不具合が多く発生している。不具合は車体下部全般に発生してはいるが、後部については巻き上げられて付着した凍結防止剤がエンジンの熱により腐食をより早めていることが考えられる。中にはデフに穴が空くといった事例も報告されている。車体前方では、今回の事故の原因でもある「Fジャッキアップポイント」にも腐食による不具合発生の報告があり、こまめな下部洗車、防錆剤の塗装、各部位の定期的な点検の実施が求められる。 |
|
| 4.腐食に対する点検の実施は26社中22社が実施しているが、2週間ごと、1ヶ月ごと、3ヶ月ごと、12ヶ月ごとと各社点検周期はまちまちである。また、点検を実施している箇所もまちまちで、点検方法は目視。今回の事故も目視での点検で終わっており、ハンマーによる打音点検を実施していたなら、防げた可能性も考えられることから、点検部位によっては目視以外の方法での点検を実施すべきと考える。また、26社中24社については、「運輸規則第45条第1項」に基づく点検基準を社内規定で定めておらず、特に頻繁に高速道路を走行する「高速乗合バス」の凍結防止剤散布による車体への影響を十分配慮した車両管理にはなっていないものと思慮される。 |
|
| 5.安全な運行に問題があると判断し、修理が必要な場合の依頼先は1/3が自社及びグループ内の整備工場、2/3がディーラー、専業工場、車体整備工場。不具合の発生部位によっては廃車処分となる模様。各社とも修理依頼先については、それなりの知識や経験、技術を持った整備工場等に依頼していることから、修理が原因となる事故、不具合の発生は考えにくい。 |
|
《まとめ》 今回発生した高速道路での事故を受けて実施したアンケートについてまとめた結果、
今後次の内容について、各事業者を指導していく必要があると考える。
● 冬期に散布される凍結防止剤による車両への影響は想像以上に大きいことから、高速道路を
走行する頻度の高い「高速乗合バス」等については、事前及び定期的な防錆剤塗装の実施、
運行後のこまめな下部洗車の実施。
● 腐食に対する点検の実施については、「運輸規則第45条第1項」に基づき、運行する道路状
況を考慮し、自社の車両について必要な点検方法を含めた点検基準の早急な作成、実施。
● 特に定期的に実施する点検の方法については、目視のみによらず、腐食が各部位の内部にも
及んでいる可能性があることから、打音点検を行う等必要に応じた点検を行うことが重要。 |
|
| 【参 考】 |
| (1) 国土交通省 「使用過程車の保守管理に関する調査分析検討会」 |