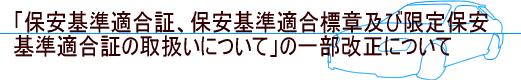| 保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の取扱いについて(平成7年3月27日付け自技第43号・自整第63号) |
|
| (※以下赤字下線部が改正箇所) |
|
道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成7年運輸省令第8号)が公布され、本年7月から施行されることとなったところであるが、改正後の道路運送車両法第94条の5第1項又は第94条の5の2第1項の規定により保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付する場合の取扱い等については別紙「保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の取扱要領」によることとしたので、関係者に周知徹底を図られたい。
なお、「保安基準適合証及び保安基準適合標章の取扱いについて」(昭和44年自整第294号)は省令の施行日の前日をもって廃止する。
附 則(平成22年1月19日 国自技第248号、国自整第120号)
1.本改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、別紙第1項(3)を加える改正規定及び別紙第4項(2)③の改正規定(別紙1(3)①に規定
する一連番号に関する情報に係るものに限る)は、平成22年5月1日から施行する。
2.施行前に指定自動車整備事業者が配布を受けた適合証綴にあっては、なお従前の例による
ものとする。 |
|
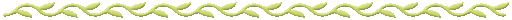 |
|
| 別 紙 |
|
| 保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の取扱要領 |
|
| 1.用 紙 |
| (1) 保安基準適合証(限定保安基準適合証として使用する場合を含む。以下「適合証」という)及び保安基準適合標章(以下「適合標章」という)となるべき用紙は、次の表のとおりワンライティング方式として編成されていること。 |
|
| 編 成 |
種 類 |
用 途 |
| 上 葉 |
保安基準適合証(控)
限定保安基準適合証(控) |
指定自動車整備事業者の交付控とする。 |
| 中 葉 |
保安基準適合証
限定保安基準適合証 |
指定自動車整備事業者の交付用とする。 |
| 下 葉 |
保安基準適合標章
|
指定自動車整備事業者の交付用とする。 |
|
|
| (2) (1)の表中の各葉に、指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)第一号様式及び第二号様式その他の保険証明書に係る事項の欄等関係通達により求められるものが、印刷されていること。 |
(3) (1)の表中の各葉に、次に掲げる不正防止対策が施されていること。
|
① 指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)第一号様式及び第二号様式(表面又
は裏面)の端部に、マイクロ文字及び製造者名並びに上葉・中葉・下葉からなる一組ごとに固
有の9桁の一連番号が印刷されていること。 |
② 中葉に地紋が印刷されていること。なお、一部の地紋は蛍光インクにより印刷されている
こと。 |
③ 下葉に、表面を複写した場合複写した紙にのみ複写をしたものであることが明確に分かる
地紋が出る用紙が使用されていること、及び、表面に地紋が印刷されていること。 |
|
| 2.記載方法 |
| (1) 適合証及び適合標章への記載は、ワンライティング方式であるので、保安基準適合証(控)(限定保安基準適合証(控)として使用する場合を含む。以下「適合証(控)」という)にボーールペン等で記載すること。 |
| (2) 指定番号欄には、当該指定自動車整備事業者(以下単に「指定整備事業者」という)に付された指定番号を記載すること。 |
| (3) 交付番号欄には、指定整備事業者における適合証の交付順による暦年または年度ごとの一連番号を記載すること。 |
| (4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(以下「法」という)第94条の5第4項の点検及び検査を、複数の自動車検査員が分担して行った場合の自動車検査員の証明欄には、最後に検査の実務を行った自動車検査員の指名を含めて記名及び押印をすること。この場合において、当該証明書欄に点検及び検査の実務を行った全ての自動車検査員の記名及び押印が困難となるときは、当該証明書欄の自動車検査員名の記名に続き、外何名と記載し、この自動車検査員の記名及び押印は適合証及び適合標章の余白に行うこと。また、自動車検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の年月日は、最後に検査の実務を行った年月日とすること。 |
| (5) 指定整備事業者の名称及び所在地等の欄には、ゴム印により各葉ごとに押印しても差し支えない。 |
(6) 次の欄には、当該自動車検査証等の当該事項を転記すること。
イ 使用者 ロ 乗車定員 ハ 最大積載量 ニ 用途 ホ 車両総重量 |
| (7) 保険期間欄には、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という)の保険期間(自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間)を転記すること。この場合において、当該自動車に係る保険証明書が二枚以上にわたる場合には、最初の保険証明書に係る保険期間の最初の日及び最後の保険証明書に係る保険期間の最後の日を転記することでたりる。 |
| (8) 適合標章の有効期間起算日を表示する欄には、ボールペン等により黒色で記載すること。 |
| (9) 適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印を用いて赤色スタンプインクにより明瞭に押印すること。 |
| (10) 適合標章(表)の自動車登録番号または車両番号欄には、サインペン等により黒色で記載すること。 |
|
| 3.適合標章の表示 |
| (1) 適合標章を交付した場合には、法第94条の6第1項の規定により適合標章の番号を指定整備記録簿に記載すること。 |
| (2) 「道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令」(平成20年国土交通省令第59号)による改正後の適合標章を前面ガラスに張り付けて表示する場合は、適合標章の中央点線のところから二つ折りとし、適合標章の有効期間が記載された面を、前面ガラス内側に次の①~③のいずれかにより貼り付けるまたは装着すること。なお、この場合、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第29条の規定に注意すること。 |
① 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方のガラスの上部。この場合
において、適合標章に記載された有効期間及び自動車登録番号または車両番号の認識が困難と
なるときは、車室内後写鏡に隠れる範囲内において認識が可能となる位置まで下方にずらした
位置。 |
② ①に掲げる自動車以外の自動車にあっては、全面ガラスの上部であって運転者席から最も
遠い位置。この場合において、適合標章の認識が困難となるときは、認識が可能となる位置ま
で下方にずらした位置。 |
③ ①もしくは②による表示が困難な場合または運転者が交通状況を確認するために必要な視
野を妨げるおそれのある場合は、運転者が交通状況を確認するために必要な視野を妨げるおそ
れの少ない位置であって適合標章の認識が可能となる位置。 |
| (3) 適合標章を前面ガラスに貼り付けまたは装着しない場合は、有効期間を記載した表面を自動車前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示すること。 |
| (4) 2(4)の取扱いより、適合標章の余白に、自動車検査員の記名及び押印がある場合は、当該余白部を折り返し、適合標章と併合して表示するよう依頼者に対して教示すること。 |
| (5) 有効な自動車検査証及び検査標章が交付され、交付された検査標章を表示した場合において、前面ガラスに貼り付けられまたは装着されている適合標章を速やかに取り外すこと。 |
|
| 4.用紙配布等 |
| (1) 各地方自動車整備振興会(以下単に「自動車整備振興会」という)は、適合証及び適合標章となるべき用紙の綴(以下「適合証綴」という)を、指定自動車整備事業者からの求めに応じ、配布すること。 |
| (2) 自動車整備振興会は、次の各号に掲げるところにより、適合証綴の保管及び配布について管理すること。 |
| ① 当該管理の責任者として保管責任者を定めること。 |
| ② 配布台帳(別表1及び別表2)を作成すること。 |
③ 適合証綴を授受した場合、速やかに適合証綴の表紙に綴番号を押印し、配布台帳(別表1)
の受入欄に当該綴番号を、同台帳備考欄に1(3)①に規定する一連番号に関する情報を、記入す
ること。 |
④ 印刷不良等の適合証綴については、処理状況を配布台帳(別表1)の備考欄に記入すること
。 |
⑤ 適合証綴を指定自動車整備事業者に配布する際は、次の各号に掲げるところによること。
イ 配布台帳(別表2)に記入すること。
ロ 当該指定自動車整備事業者の授受出納簿(5(1)の規定に基づき作成されたもの(別表
3))の記載内容を確認の上、当該授受出納簿の日付及び受入欄への記入及び取扱者印
(振興会)欄への押印を行うこと。 |
(3) 自動車整備振興会は、適合証綴の配布の際、価格を明示すること。なお、適合証綴は自動車
整備振興会が製造者から直接調達し、配布の際に明示する価格は実費相当とし、指定自動車整備事業者から求めがある場合は当該価格について適切に説明すること。 |
| (4) 削 除 |
|
| 5.交付状況の把握等 |
| (1) 指定自動車整備事業者は、適合証綴の授受出納簿(別表3)を作成し、適合証綴数の収受状況を把握すること。 |
| (2) 指定自動車整備事業者は、適合証綴の保管責任者を定め、管理すること。 |
| (3) 指定自動車整備事業者は、適合証及び適合標章の交付状況を把握すること。 |
| (4) 指定自動車整備事業者は、適合証綴を使用後2年間保存しておくこと。 |
| (5) 指定自動車整備事業者は、次に掲げる不正防止対策を講ずること。 |
① 適合証又は適合標章を書き損じた場合は、記載面を朱末し、当該適合証及び適合標章を適
合証綴から切り離すことなく適合証(控)とともに保存しておくこと。 |
② 適合標章を交付しない場合は、当該適合標章の表面を朱末し、当該適合標章適合証綴から
切り離すことなく適合証(控)とともに保存しておくこと。 |
③ 電算機により適合証又は適合標章の記載(自動車検査員の氏名及び印を除く)を行う場合
は、適合証綴の使用過程において適合適合証又は適合標章を切り離して使用することは差し支
えないが、散逸しないよう注意し、適合証綴の使用が終了した時点で確実に編綴、保存するこ
と。 |
|
| 6. 削 除 |
|
| 7. 削 除 |
|
| 別 表1 ~ 3 (略) |